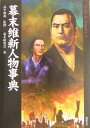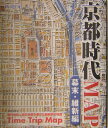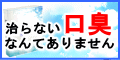[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 【1000円以上送料無料】新島八重を歩く 激動の幕末〜昭和を生きた会津女性の足跡/星亮一/戊... |
![【送料無料】るろうに剣心[完全版] (1-22巻全巻)漫画全巻セット【中古本】【中古】【ブック...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fzenkanmanga%2fcabinet%2fh2kr%2fu-ru-06.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fzenkanmanga%2fcabinet%2fh2kr%2fu-ru-06.jpg%3f_ex%3d80x80) 【送料無料】るろうに剣心[完全版] (1-22巻全巻)漫画全巻セット【中古本】【中古】【ブック... |

歴史小説は“史実”か“虚構”か、という対比には意味がない。作家も歴史家も、自分の生きている時代のなかで、ある時代を切り取り、対象として書く。歴史を描くうえで、両者の差はない。史実が書かれているかどうかではなく、記述の“作法”に意味がある。本書では、「国民作家」司馬遼太郎作品のなかでもとくに人気の高い『竜馬がゆく』と『坂の上の雲』を、作品全体を通してたんねんに読み込んでいく。2作品で司馬が書いた、あるいは書かなかった幕末・明治を、小説の対象となった時代・小説が書かれた時代・そしてわれわれが読んでいる今現在=「三つの時間軸」で読む、はじめての試みである。読み手が“いま”を背景に、作品をどう読むかも問われるのだ。 【目次 第1章 いま、司馬遼太郎を読むこと/第2章 『竜馬がゆく』を読む(近代日本の出発点としての「明治維新」/近代人・司馬のみた「近代」形成の論理/1960年の坂本竜馬像/司馬遼太郎の明治維新像/歴史学の明治維新像)/第3章 『坂の上の雲』を読む(描かれる「国民国家」の試練/文明/民族/帝国―19世紀の世界史像と日本像/「戦争の語り」(認識/記述の作法をめぐって)/司馬遼太郎が描いたこと/描かなかったこと/描けなかったこと)

歴史小説は“史実”か“虚構”か、という対比には意味がない。作家も歴史家も、自分の生きている時代のなかで、ある時代を切り取り、対象として書く。歴史を描くうえで、両者の差はない。史実が書かれているかどうかではなく、記述の“作法”に意味がある。本書では、「国民作家」司馬遼太郎作品のなかでもとくに人気の高い『竜馬がゆく』と『坂の上の雲』を、作品全体を通してたんねんに読み込んでいく。2作品で司馬が書いた、あるいは書かなかった幕末・明治を、小説の対象となった時代・小説が書かれた時代・そしてわれわれが読んでいる今現在=「三つの時間軸」で読む、はじめての試みである。読み手が“いま”を背景に、作品をどう読むかも問われるのだ。 【目次 第1章 いま、司馬遼太郎を読むこと/第2章 『竜馬がゆく』を読む(近代日本の出発点としての「明治維新」/近代人・司馬のみた「近代」形成の論理/1960年の坂本竜馬像/司馬遼太郎の明治維新像/歴史学の明治維新像)/第3章 『坂の上の雲』を読む(描かれる「国民国家」の試練/文明/民族/帝国―19世紀の世界史像と日本像/「戦争の語り」(認識/記述の作法をめぐって)/司馬遼太郎が描いたこと/描かなかったこと/描けなかったこと) 【著者情報 成田龍一(ナリタリュウイチ) 1951年、大阪府生まれ。早稲田大学大学院修了。現在、日本女子大学教授。専攻は近現代日本史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです

内容情報 島国に生きる日本人は、常に「一国平和主義」という願望を持っている。これに起因する「問題の先送り」や「厳しい現実を直視しない」という民族的欠点は、国際社会において日本をしばしば不利な状況に陥れてきた。多くの人命と財産を失った挙げ句、最も損なかたちで行われた幕末の開国は、その典型である。大変革期の真っ只中、時代を動かした男たちはどのような決断をしていったのか?井沢元彦が、独自の視点で日本史を斬る。 【目次 近藤勇/土方歳三/沖田総司/永倉新八/斎藤一/原田左之助/井上源三郎/山南敬助/伊東甲子太郎/藤堂平助〔ほか〕 【著者情報】 井沢元彦(イザワモトヒコ) 1954年名古屋市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、TBS報道局に入社。在職中の80年に『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞し、作家デビューを果たす。退社後、執筆活動に専念。独自の歴史観でテーマに斬り込む作品で人気を博している

大ベストセラー『昭和史』の著者が、多くの才能が入り乱れた激動の時代「幕末」を語り下ろす。黒船来航から西南戦争までを丁寧に紐解いた待望の書。内容情報】(「BOOK」データベースより) 多くの才能が入り乱れ、日本が大転換を遂げた二十五年間―。その大混乱の時代の流れを、平易かつ刺激的に説いてゆく。はたして、明治は「維新」だったのか。幕末の志士たちは、何を目指していたのか。独自の歴史観を織り交ぜながら、個々の人物を活き活きと描いた書。 【目次 「御瓦解」と「御一新」/幕末のいちばん長い日―嘉永六年(一八五三)ペリー艦隊の来航/攘夷派・開国派・一橋派・紀伊派―安政五年(一八五八)安政の大獄/和宮降嫁と公武合体論―文久二年(一八六二)寺田屋事件/テロに震撼する京の町―文久三年(一八六三)攘夷決行命令/すさまじき権力闘争―元治元年(一八六四)蛤御門の変/皇国の御為に砕身尽力―慶応二年(一八六六)薩長連合成る/将軍死す、天皇も死す―慶応二年(一八六六)慶喜将軍となる/徳川慶喜、ついに朝敵となる―慶応四年(一八六八)鳥羽伏見の戦い/勝海舟と西郷隆盛―慶応四年(一八六八)江戸城の無血開城/戊辰戦争の戦死者たち―明治元年(一八六八)会津若松城開城/新政府の海図なしの船出―明治四年(一八七一)廃藩置県の詔書/国民皆兵と不平士族―明治六年(一八七三)征韓論に揺れる/西郷どん、城山に死す―明治十年(一八七七)西南戦争の勝者/だれもいなくなった後―明治十一年(一八七八)参謀本部創設 【著者情報 半藤一利(ハンドウカズトシ) 1930年東京生まれ。東京大学文学部卒業後、文藝春秋に入社。「週刊文春」「文藝春秋」編集長、取締役などを経て作家に。『漱石先生ぞな、もし』で新田次郎文学賞、『ノモンハンの夏』で山本七平賞、『昭和史1926‐1945』『昭和史 戦後篇1945‐1989』で毎日出版文化賞特別賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)